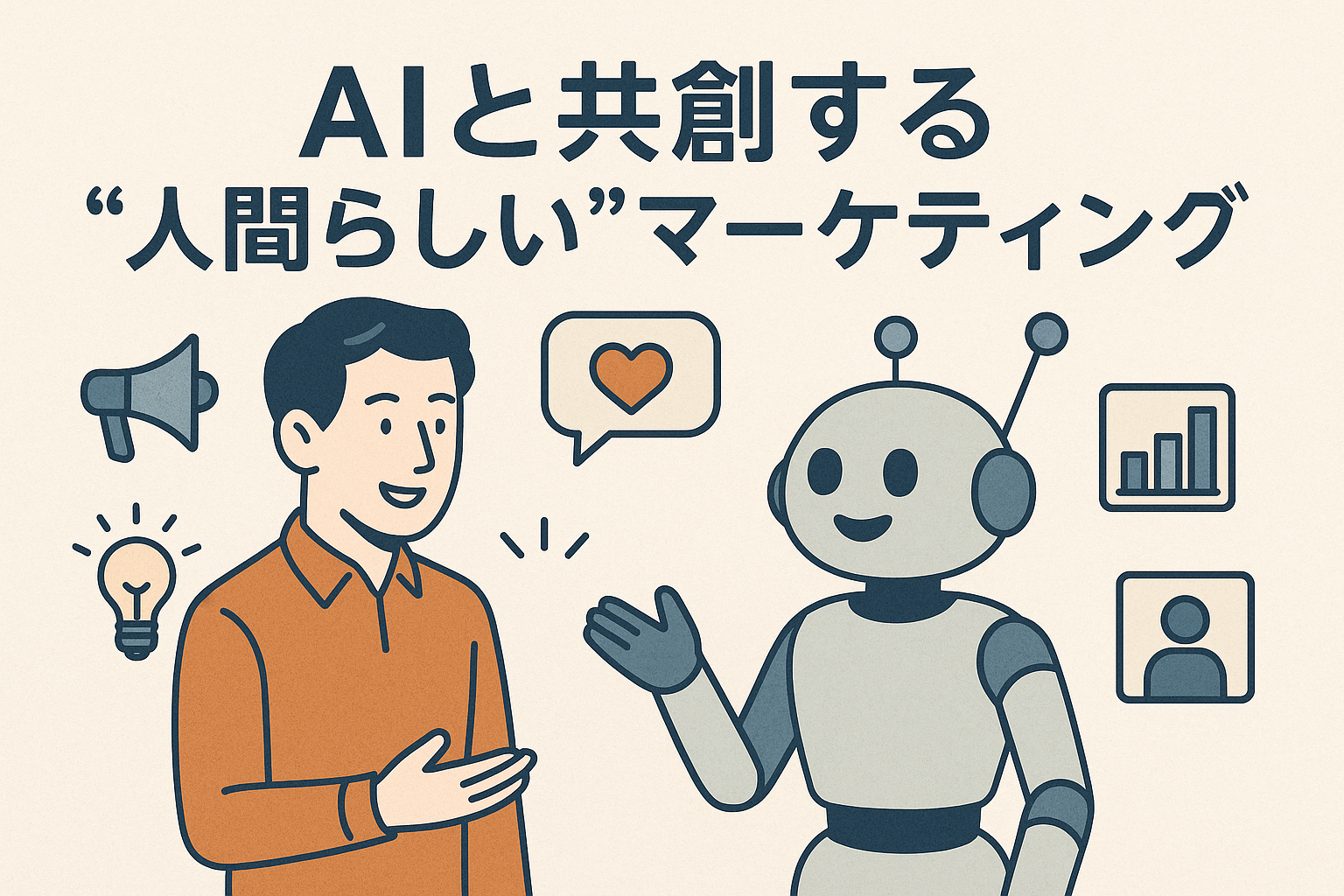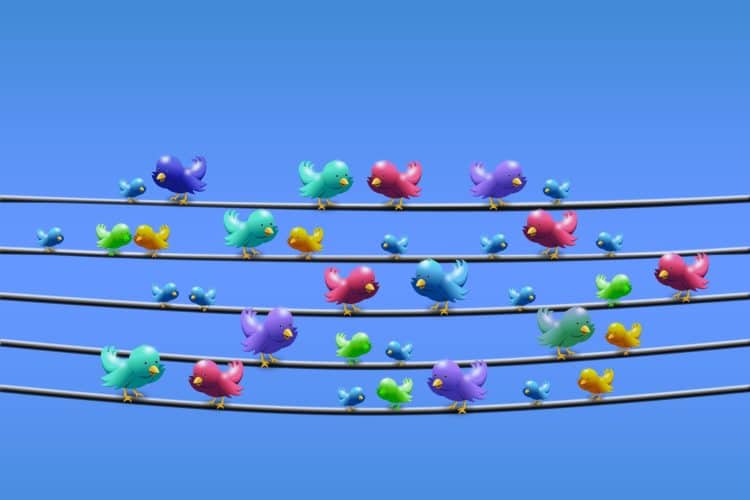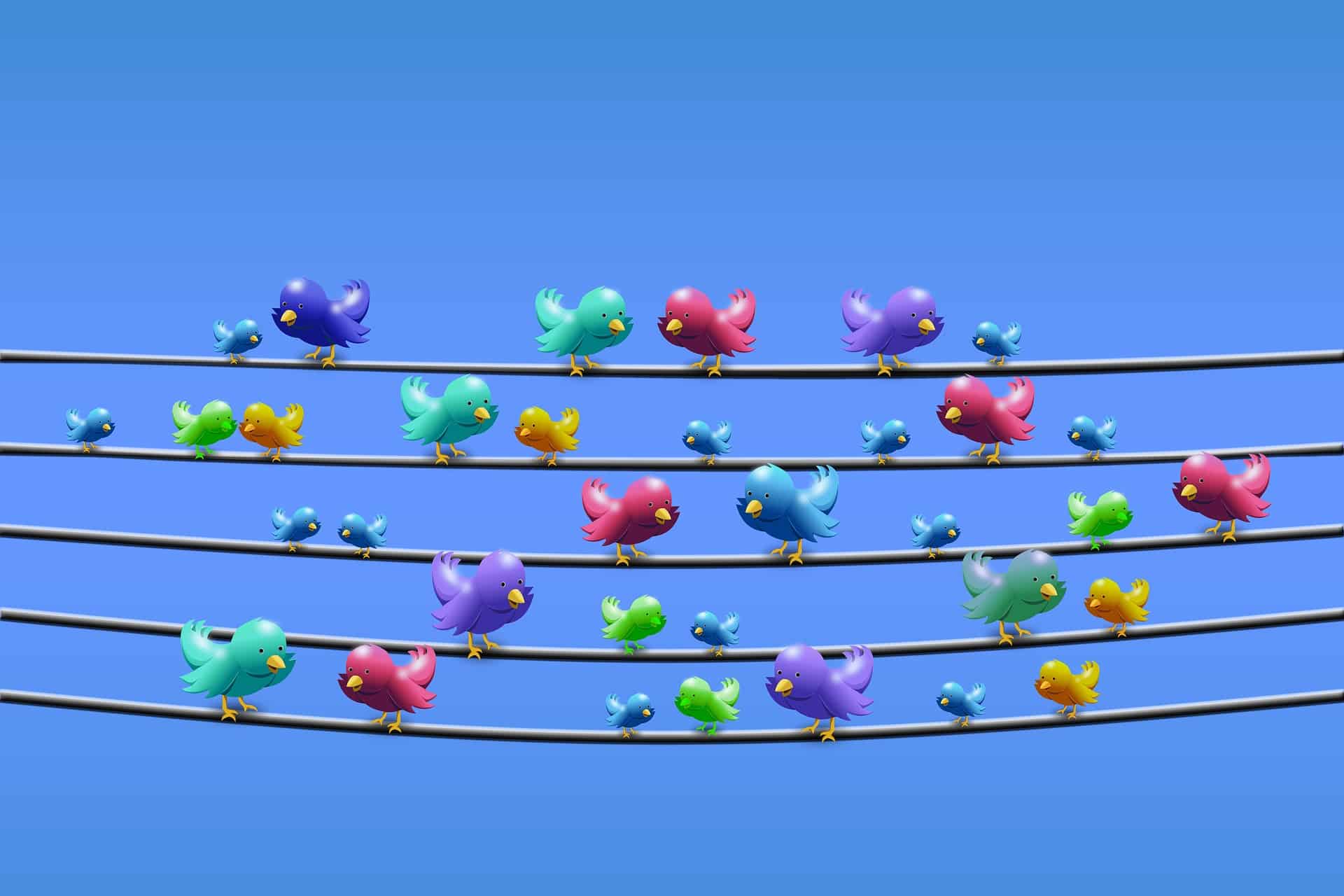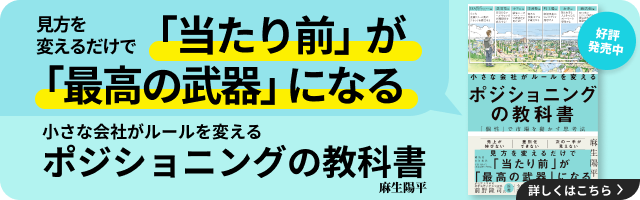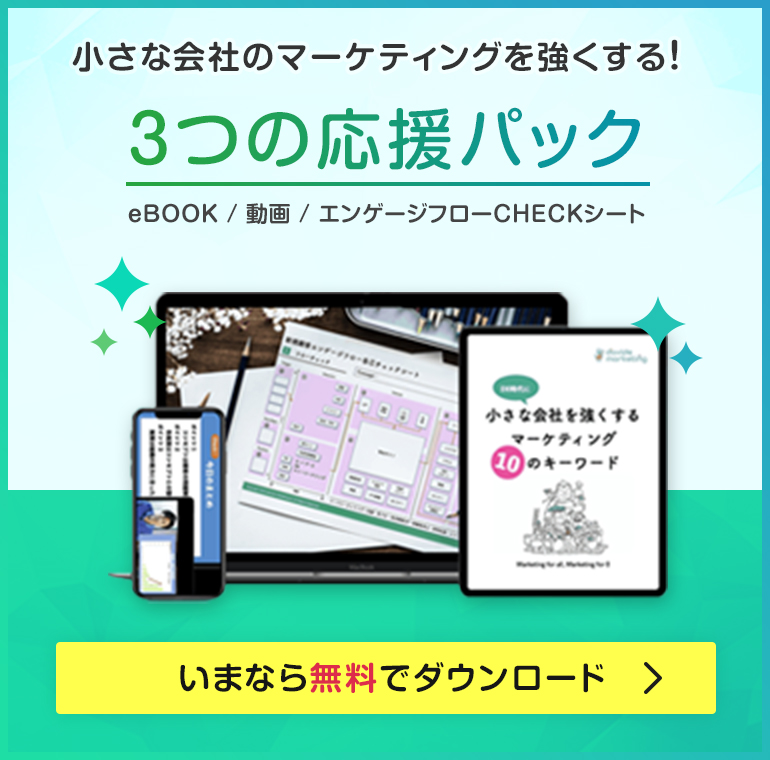顧客は、5つの異なる時代背景と価値観の上に立っている。
マーケティング5.0は、テクノロジーの力で“個”に寄り添うマーケティングを実現しようとする思想です。しかしその“個”も、完全に孤立した存在ではありません。人は時代の中で育ち、周囲の世代との関係性の中で価値観を育んでいます。
この視点を持たずに、パーソナライズを語ることはできません。今、改めて「世代」を起点にマーケティングを見直す必要があるのではないでしょうか。
1.「5世代」の理解が、マーケティング5.0を深める
マーケティング5.0で注目されているのが、次の5つの世代です。
・ベビーブーム世代(1946〜64年)
・X世代(1965〜80年)
・Y世代/ミレニアルズ(1981〜96年)
・Z世代(1997〜2012年)
・α世代(2013年〜)
それぞれの世代は、社会背景やテクノロジー環境、価値観の形成プロセスが異なります。つまり「同じ商品」「同じ情報発信」では、響き方が大きく変わってくるということです。マーケターはこの違いを理解した上で、「誰に・どの文脈で・どう伝えるか」を再設計する必要があります。
2.ベビーブーム〜X世代:「信頼」と「安心」を軸に
この世代はテレビ・新聞・折込チラシといったマスメディアを中心に育ち、「企業=信頼される存在」という意識が根強くあります。
一方で、ITへの習熟度には個人差があり、デジタルのスピード感や文脈に戸惑いを感じることも少なくありません。
ここで効果的な一つの例が、「懐かしさ×安心感」を演出するマーケティングです。
たとえば:
-
昔ながらのパッケージデザインを復刻
-
丁寧なメール文面や紙DMを併用したキャンペーン
-
実店舗でのリアルな接客との連携
また、チャットボットやFAQも“無機質”にならないよう、語尾やトーンを「やわらかく・温かく」整える工夫が求められます。
3.Y・Z世代:「共感」と「参加」がキーワード
ミレニアル世代はデジタルネイティブの先駆けであり、SNSやEC、レビューを活用する購買スタイルが定着しています。
一方、Z世代はさらに進化し、「情報の真偽を見抜く力」「自ら発信し関与する姿勢」が強く現れるのが特徴です。
この世代へのアプローチで重要なのは、「共感できる文脈」と「参加できる余地」の設計です。
たとえば:
-
SNSで“ストーリー”を軸にした発信
-
UGC(User Generated Content)を活用したキャンペーン
-
アンバサダープログラムや投票企画による参加設計
彼らにとって、“関われる”ことは“好きになる”きっかけでもあります。
商品自体の良し悪しだけでなく、「ブランドと自分の関係性」が購買を左右するのです。
4.α世代:「遊び×学び」の体験が未来をつくる
α世代は現在10歳前後。まだ購買の主体ではないものの、将来の消費の主役です。
さらに、彼らの反応は親世代の意思決定にも強く影響します。
この世代へのマーケティングは、「教育的視点」と「没入型体験」が鍵になります。
たとえば:
-
ARやXRを使った知育×ブランドコンテンツ
-
ゲームと連動した商品体験
-
インタラクティブな動画や音声コンテンツ
ここで意識したいのは、“ブランドを好きになる”という体験を、小さい頃から自然に提供しておくこと。
それが将来のロイヤルティを育てる土壌になるのです。
5.世代別マーケティング × AI時代の実践法
「世代理解をどうデータに落とし込むか?」
ここで活躍するのが、AIによるペルソナ生成やセグメント分析です。
たとえば:
-
SNSや購買データから世代ごとの関心キーワードを抽出
-
パーソナライズされたメールのトーンを世代別に変える
-
コンテンツの訴求ポイントを世代でA/Bテストする
このように、AIの分析力を活用すれば、「年齢による想定」ではなく、「行動データに基づいた世代理解」が可能になります。
まとめ:マーケティング5.0的視点で、世代を「人」として捉える
世代別マーケティングは、人や世代を“ラベリング”するためのものではありません。
「Z世代だからこう」「高齢層にはこれ」――そうした型にはめる発想ではなく、
“その人がどんな背景で今ここにいるのか”を理解しようとすることが、マーケティング5.0的な視点なのです。
テクノロジーはあくまで“共感”を深める手段となります。
時代も価値観も異なる人たちに対して、「私たちは、あなたを理解しようとしている」と伝え、相互の理解を深める。
その姿勢こそが、ブランドの信頼をつくることにつながっていくでしょう。