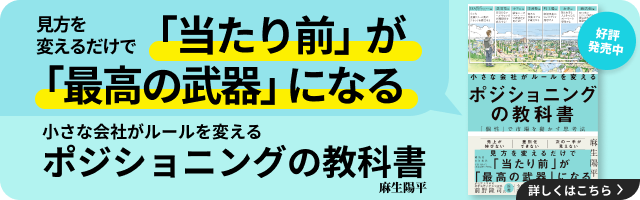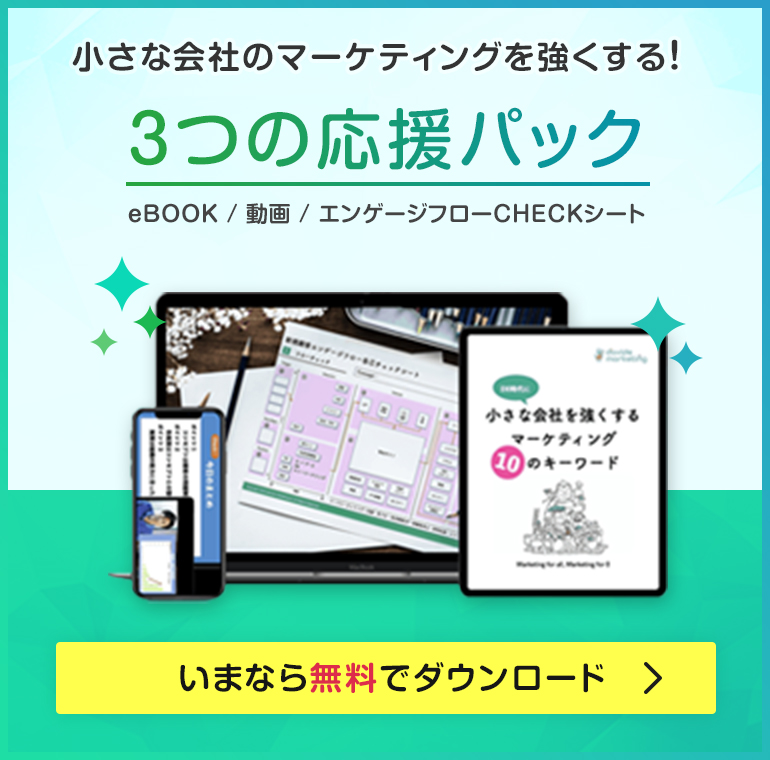COLUMN
AIと共創する“人間らしい”マーケティングとは?
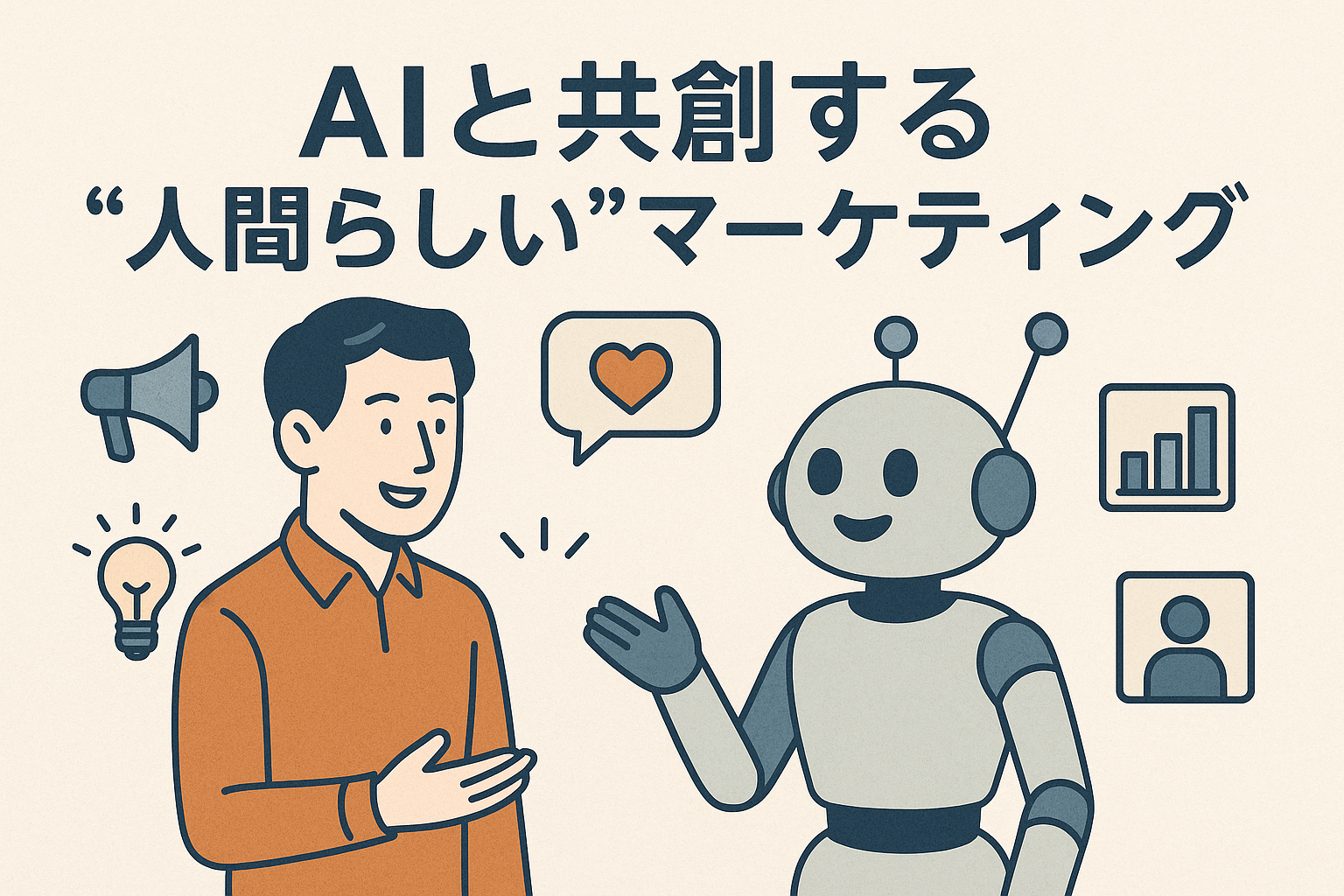
「効率化」よりも、「共感」が求められる時代へ。
AIが加速度的に進化する現代。
マーケティングの現場では、生成AIによるライティング、パーソナライズされた広告配信、データドリブンな施策設計など、これまで“人”が担っていた多くの業務が次々と自動化されつつあります。
一見すると、それは“合理的”であり、“最適”な選択のようにも見えます。
けれど私たちは、どこかでこう感じてはいないでしょうか?
「最適なはずなのに、なぜか心に残らない」
「便利ではあるけれど、なぜか共感できない」
テクノロジーが発達すればするほど、逆説的に“人間らしさ”の価値が浮き彫りになっている。
それが、マーケティング5.0時代の本質なのかもしれません。
2.「最適化」ではなく、「気持ち」に寄り添う設計へ
かつてマーケティングは、数字で管理されるものでした。
CTR、CVR、ROASといった指標が優先され、いかに効率よく結果を出すかが求められてきました。
しかし、今は状況が変わりつつあります。
たとえば、同じように最適化されたECサイトでも、「なんとなく冷たい」と感じるブランドと、「ここは好き」と思えるブランドがあります。
その差を生み出しているのが、“人間らしさ”の設計です。
つまり、ユーザーの「気持ち」にどう寄り添えるか。
その視点を持てるかどうかが、テクノロジー時代のブランド価値を左右するようになってきたのです。
3.感情を読み解く、共感アルゴリズムの可能性
では、その“人間らしさ”をテクノロジーでどう実装するか。
ここで注目されているのが、「感情解析AI」や「共感アルゴリズム」と呼ばれる技術です。
SNSの投稿、レビューコメント、チャット履歴などの自然言語から、「嬉しい」「不安」「困っている」といった感情を読み取り、それに応じたコミュニケーションを返す。
こうした技術によって、従来では拾いきれなかった“心の揺れ”を、マーケティング施策に活かすことができるようになってきました。
たとえば、問い合わせフォームで「不安」や「怒り」の感情を検知したら、AIチャットボットのトーンを自動的に「丁寧・安心」に切り替える。
こうした小さな変化が、ユーザーにとっては「この会社、ちゃんとわかってくれてる」と感じる瞬間になります。
4.ブランド“トーン”をAIに学習させる時代へ
生成AIの活用が進む中、最も重要なのは「そのブランドらしさを、いかに保てるか」です。
AIは、指示すればいくらでも文章を書いてくれます。
けれど、それが「らしく」なければ、ただの“誰でもいい情報”に過ぎません。
そこで今注目されているのが、「ブランドトーンのAI学習」です。
実際の広告文、SNS投稿、カタログコピーなどを学習させることで、語尾・構文・言い回しに一貫性のある“人格あるAI”をつくる。
この取り組みは、大手だけでなく中小ブランドでも十分実践可能です。
たとえば、ChatGPTに「このブランドのトーンは明るく、親しみやすく、でも品がある」と伝えれば、そのトーンを模したテキストが生成されます。
これはもはや「ブランドデザインのパートナー」なのです。
5.マーケターの役割は“共感設計士”になること
ここまでくると、マーケターの役割は大きく変化します。
単なる数字の最適化ではなく、「顧客の心の機微を汲み取り、それをどう体験に変えるか」を設計する存在。
いわば、“共感デザイナー”のような立場です。
たとえば、AIが分析した顧客の声から、「このブランドには、安心感を求めている人が多い」と気づいたとします。
そのとき、サイトの色味をやわらかくする、チャットの第一声を変える、パッケージに一言メッセージを添える……そんな小さな施策の積み重ねが、共感を育てるマーケティングになります。
AIはツールではありますが、そこに“心”を通わせるかどうかは、私たち人間次第なのです。
まとめ:「AIと共創する」ことは、「人間らしさ」を深めること
マーケティング5.0は、テクノロジーだけで完結する考え方ではありません。
むしろ、テクノロジーによって「人間の価値」をより深く浮かび上がらせる思想です。
効率化のためだけにAIを使うのではなく、「人の気持ちをより理解するためにAIを活用する」。
この発想があってこそ、ブランドは“選ばれる理由”を持つことができるのです。
そして何より、私たち自身もまた、AIとの共創によって「より人間らしくなる」ことができるのではないでしょうか。
RECOMMEND
関連記事・動画CATEGORY
TAG
RANKING
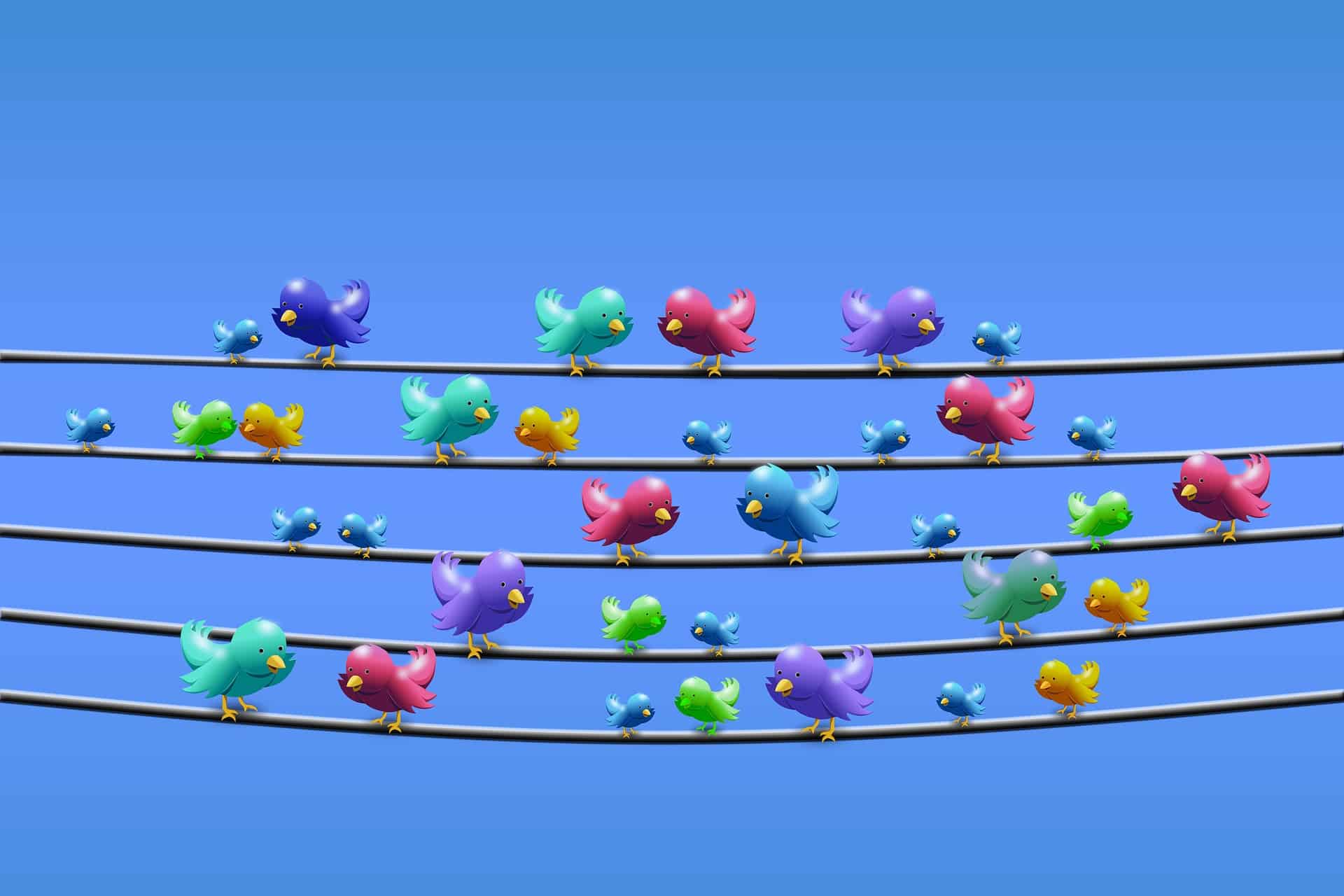
5Aとは?コトラーが提唱するSNS時代のマーケティング手法の特徴を解説

USJから学ぶ「ターゲットを狭く定義しすぎない」理由

ディズニーランドで考える4P分析で本当に大切なこと

ブランディングで大切なこと。差別化から独自性へ

インナーブランディングとは?スタバの事例で学ぶその重要性

ウォルト・ディズニーと「ブランディングの科学」から学ぶターゲットの考え方

人間中心の体験を設計するサブスクリプションモデル。「経験価値」とは?

小さな会社が強いブランドをつくる方法。ブランドづくりには順序がある。

今こそマーケティング3.0。在り方は縦の関係から横のつながりへ

「独自性」を生む強いブランドづくりはブランド・アイデンティティから